歌集バシー海峡
【書名】歌集 バシー海峡
【著者】中嶋秀次
【発行日】昭和五十一年八月十九日
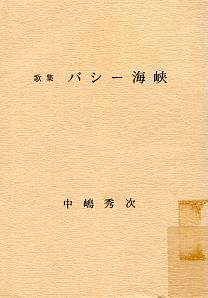
目くるめく 海の碧さに おどろきぬ 風の蒙古に 住み馴れし身は
果てしなき 積荷の山を 朱にそめる 釜山埠頭の 夏の夕ぐれ
灯がゆれる 伊万里の町の 灯がゆれる 耐えいるこころ 揺さぶるように
今ぞ征く 大船団の たのもしさ 水の涯てより 涯てに連なる
よろめきつ 逆巻く海に 嘔吐しぬ 衛兵われの 銃にぎりしめ
見えぬ敵 足下にひそむ 気配して 藍の静寂(しじま)を ジグザグに航く
この一夜 つつがなかれと 救命胴衣(ブイ)を着る 戦友(とも)の横顔 いのるがごとし
燃えているは 護衛空母か 油槽船(タンカー)か バシー海峡 二十二時五分
必殺の 爆雷の雨 ふる海を いずくに潜む 白面の敵
「早く夜が 明けねぇかな」と 髭面が 肩を落として しんみりという
筏ごし 無言で挙手の 礼すれば にっこり笑う 小宮山中尉
船呼ぼう 筏の兵の 涙ごえ いまさら恥も 外聞もなし
章魚(たこ)のごと わが手を食える ものならと 戯れ言(ざれごと)いえど 誰もわらわず
じりじりと 筏の竹に 照りかえる バシーの海の 悪魔の太陽
「湯をくれし 昨夜の女は いづくか」と 狂える戦友(とも)の 真顔にて問う
筏より 伸べしわが手を 払いのけ 空虚ろな眼にて 泳ぎて行きぬ
「俺の分 なぜ残さぬ」と 怒鳴りたる われあさましや 餓鬼となりぬる
褌(ふんどし)を 洗いて乾して しめなおす ちょっぴりなれど きょうのよろこび
思わずも 剣を掴みて 近づける 艦を見つめぬ 呼吸ひそめては
「眠るなよ 寝れば死ぬぞ」 覗きこむ 水兵さんの 幅ひろき胸
あとがき
この苛烈なる体験を語るのに、短歌という小詩型をかりたことを私は悔んだ。刹那、刹那のあえかなる抒情を謳いあげるには真いみじきこの小詩も、バシー海峡を舞台に展開される民族エネルギーの激突ともいうべき戦争というダイナミックな悲劇を描写するのには、何としても力不足の感を否みえなかった。云いわけと思われても仕方がないが、譬えていうならば、オーケストラの全楽器を駆使してこそ醸し出しうる重量感をたった一挺のギターで表現しようとするような、そんな心もとなさが付きまとい、如何しても謳いきれぬものを覚えていくたび筆を擱ろうとしたことか。それなのにその古いギターが棄てきれず、やるせない音色に魅せられ漂流の歌を侘しく唄いつづけてきた私を不思議にも思う。思い起こすだに、ぞっとする悪夢のような漂流の日々。(怒涛山なすバシーの暴風雨、茹だるような太陽の熱射、筆舌に尽しえぬ飢渇、気の狂いそうな孤独感。━━━━)
そうした大自然の苛酷さにさいなまれながらも、一坪足らずの竹筏にすがり歯をくいしばって生きてきた十二日間のあの血の滲むような思いを、印象の鮮烈なうちに書き止めたい何とか物したいと迸しるような気持ちでペンを執ったのは、昭和十九年も秋の初め、台湾高雄陸軍病院第十三病棟の固いベッドに漸く寝がえりの打てるようになった日のことである。キニーネの匂いのしみついた薄暗い病室で、台湾人の看護婦から貰ったザラ紙のノートにちびた鉛筆を走らせながら、四ヶ月にわたる療養生活のつれづれをひたすら歌作にいそしんだものである。
あれから、ざっと三十年になる。所詮、人生は漂流である。悠遠の太初より無限の未来に向って流れつづける生命の大河の岸で、人の子は、いったい何を考え、何処に行こうとするのか。私の肉体を形成する細胞が、この胸の哀しみを知らないように、わたしたち宇宙の細胞は宇宙の心を知らない。然も、彷徨える人の子の生涯は、無限なる時の流れの中にあって、さながら瞬きの間にもにて儚いのに。━━━━
だけど、わたしは思う、儚きがゆえにいみじく有限なるがゆえに尊いことを。そして、わたしの生涯に残された時間も、もうそんなに長くはない。これまでに、勧められるまま、この歌集を世に出そうとしたことは再々あったが、その度に、どうしても蒸留しきらぬ青臭さが鼻につき、心がくじけてよう為しえなかった。謳いおおせぬところは数々あるが、ともあれ、苦しみ多き世代を生きたある父親のわかき日の人間像を描き出すことが、不肖のわが子をふくめ、次代をになう人たちに何らかの示唆をもたらすであろうことを信じ、敢えて、わが爪跡を残さうと思う。
一九七五年八月十九日
中華民国台北市仁愛路の寓居にて
中 嶋 秀 次